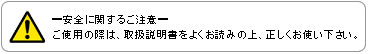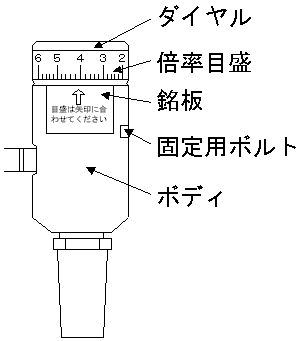オートミキサー・サーボミキサーAUTO MIXER/SERVO MIXER
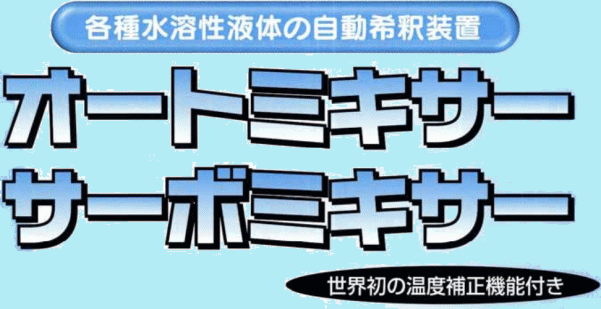
希釈倍率バルブの安定性
各目盛りにおける希釈性能は、駆動流体(工業用水)の圧力、吸引する原液の粘度(温度)が一定であれば再現性は十分にあり安定しています。
精度は希釈濃度で±0.15%より良好です。
希釈装置の使用例
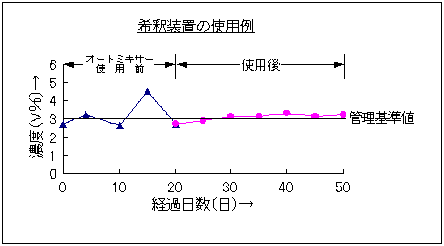
基本配管および注意事項
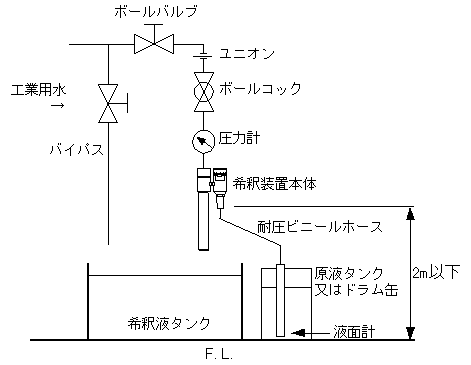
▲基本配管1
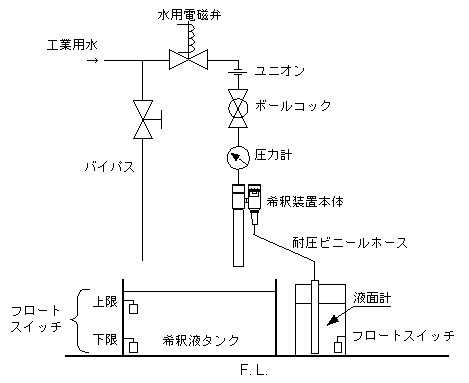
▲基本配管2
- 水道水配管へのオートミキサーの取り付けは、逆流により水道水への液の混入が考えられますから絶対に行わないで下さい。
- オートミキサーは希釈液タンクの上部に取り付けて下さい。ただし、希釈液が吐出するとき、液が拡散して出ますから下図①~③のようにして下さい。
- 希釈液中に吐出側が浸漬していると、希釈装置が停止中でも”サイホン”現象により希釈液が原液タンク中へ流入しますので、必ず希釈装置は希釈液の上限レベルより上の位置に配管して下さい。
- 原液タンクは希釈装置により下の位置に設置して下さい。もし原液タンクが希釈装置より高い位置にありますと、レベル差により希釈装置が停止中でも希釈液願国流入しますので注意して下さい。ただし希釈装置と原液タンク上限レベルとの距離が離れすぎると原液の吸引力が低下しますから、2m以内が限度です。
- 原液タンクと希釈装置の接続は、耐圧ビニールホースを推奨します。ホース内径は15mmです。
長さは水平方向で10mが限度で、これ以上長くなると性能に影響を与えますので注意して下さい。
- 希釈装置の吐出口は、直接希釈タンクへ開放形で流入させる方法が標準仕様であり、配管にて希釈液を離れた場所へ送る場合、背圧、脈動により希釈倍率が安定しません。
- 駆動流体(工業用水)に圧力変動が生じる場合は性能図のごとく希釈濃度がばらつきますから、このような時は定流量弁、もしくは温水器用減圧弁の使用を推奨します。
- 原液吸入側に、原液逆流防止弁を取り付けることは、希釈率が変化しますから行わないで下さい。
- 希釈装置を取り付ける場合にユニオンを使用しますと、希釈倍率目盛りの設定を正面の位置で行うことが可能で便利です。
- 遠隔操作および自動化をする場合は、基本配管に示しているバルブに水用電磁弁を使用し、フロートスイッチと組み合わせることにより可能です。
- 自動補給方式を採用する場合は、希釈タンクの50%以下の位置で作動するように設定して下さい。
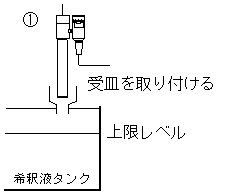
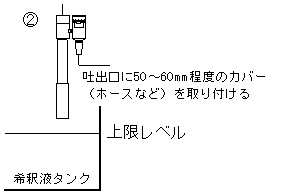
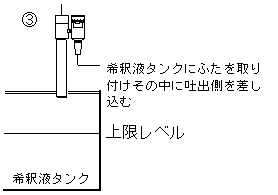
希釈倍率目盛りの設定方法
- 希釈装置に工業用水を流して、取り付けた圧力計で圧力を読む(圧力0.08Mpa{0.8Kgf/cm2}以下の場合は本装置の使用はできません)。
- 希釈する原液の所要倍率(または濃度)と粘度を調べる。
- 性能図より希釈倍率目盛りを選定し、ダイヤルを回して選んだ目盛りを矢印に合わせる。
- 希釈装置を作動させ希釈液の倍率(濃度)を測定し、所要の倍率が得られることを確認する。
- 4で測定した希釈倍率が性能図からずれている場合はダイヤルで調整する。
- 調整が終わったら固定用ボルトを締めてダイヤルを固定する。
- 高濃度の原液は温度による粘度変化が著しいので、夏場、冬場にダイヤルを調整する必要がある。
(注:オートミキサーF-20E性能図参照)
希釈装置のオプションセット
セット内容 数量 希釈装置本体 1式 ユニオン 1式 径違いチーズ 1式 ボールコック 1式 ニップル 4式 ブッシュ 1式 圧力ゲージ 1式 エルボ 1式 液面計 1式
液面計はドラム缶用または18L石油缶用の2種類がありますので、セットで注文の際はご連絡ください。
取扱上の注意
- 工業用水に多量の錆、スライム等が混入している場合に、ノズルを目詰まりさせることがありますから注意して下さい。
- 薬剤、油剤の種類によりノズル・ディフューザ部に固形物が固着して、希釈倍率(濃度)に誤差を生じることがあります。希釈濃度が大きく”ブレ”たときは、本体を点検して下さい。
固着している場合は、油、溶剤等で洗浄して下さい。
- 原液の倍率(濃度)を適時測定して性能をチェックして下さい。
- 希釈液を吸入しないまたは希釈倍率が極端に小さい場合は、
- 工業用水の圧力が動作時に0.08MPa(0.8Kgf/cm2)以下である。ことが考えられるので,これらへの対応を行って下さい。
- エアを吸引している。
- ノズル・ディフューザ部が原液の固形分で詰まっている。
- 原液の粘度が高すぎる。
- 工業用水が原液側に流入する原因は、工業用水の圧力が高すぎる(0.2MPa以上)または低すぎる(0.08MPa以下)の場合に発生します。
オートミキサのトップページへ 前のページへ 次のページへ
オートミキサー・サーボミキサーのカタログ・取扱説明書 (詳細はこちらから)
 オートミキサー・サーボミキサー カタログ・取扱説明書
オートミキサー・サーボミキサー カタログ・取扱説明書
水溶性切削液などの希釈装置,オートミキサーとサーボミキサーの取扱説明書とカタログを兼ねたものです。
オートミキサー・サーボミキサーをご検討の方は,必ずこのPDFの8ページ目(最後のページ)の注意事項を必ずお読み下さい。。
本製品は,豊田化学工業株式会社様の製品です。
オートミキサーに関する詳細
外観寸法図・名称・材質
標準仕様・希釈装置の性能・オートミキサーF-20およびF-70の性能図
オートミキサーF-20EおよびサーボミキサーSV-20の性能図
希釈倍率バルブの安定性
希釈装置の使用例
基本配管および注意事項
希釈倍率目盛りの設定方法
希釈装置のオプションセット
取り扱い上の注意事項
オートミキサーによる希釈自動制御システムのご案内水溶性切削液・水溶性圧延油自動希釈設備
オートミキサーの設置と設定に関するノウハウ
- 駆動用流体(水)の流量を一定に管理する(たとえばF-70の場合毎分70リットル、F-20の場合毎分20リットルとします)。可能であれば水用の流量計をご使用下さい。
- 駆動用流体(水)の圧力を一定にします。基本は0.1MPaでオートミキサーに供給します。圧力0.2MPa以上であっても変動がなければ問題ない場合があります。水の供給配管には圧力計の取り付けが必要です。
- 一度に希釈液を作る量がF-20の場合20リットル以上、F-70の場合は70リットル以上になることを目安にします。駆動用流体である水がオートミキサーを通過したときに、原液の吸引力が生まれますから、原理的には希釈開始から少しの間はオートミキサーから水しか出ません。
オートミキサーと原液タンクの原液の液面との高低差を小さくすると、水しか出ない時間を短くできます。
- 必ず定期的に希釈後の液は糖度計を使い、濃度の計測と管理を行って下さい。糖度計(アタゴ製)は安価に入手できます。
- オートミキサーの内部に原液に含まれる固形成分が付着して、本体のダイヤルで希釈率をコントロールしているオリフィスの内径が付着物により小さくなり、希釈率が変動します。そのため、オートミキサー本体を定期的に取り外し、清掃しなければなりません。
オートミキサー本体を湯に浸漬しておくだけでも十分に付着物が除去できる場合もありますが、分解清掃が必要な場合もあります。
清掃の頻度は、ご使用になる原液によって異なります。
オートミキサーの取り外しを容易にするため、オートミキサの駆動流体の入るところ(25Aメスネジ)に、ニップルを介してユニオンを取り付けておくと容易に配管からの取り外しができます。
オートミキサーの清掃の頻度にもよりますが、複数のオートミキサーを設置頂き、バルブ切替ができるように配管を組んで頂くと、希釈装置を停止させることなくオートミキサーの清掃ができます。
- オートミキサの吐出口が希釈液タンクの液面の中に入っている場合(吐出口の先にホースを取り付けている場合も同じ)、希釈液がサイフォン現象により原液タンクまたは駆動流体の配管側に逆流します(実際に逆流して原液タンクに希釈液が入った事例があります)。
オートミキサー・サーボミキサーカタログ・取扱説明書の6ページの「基本配管及び取付時の注意事項」の図8~10をご参照下さい。
オートミキサー・サーボミキサーカタログ・取扱説明書(PDFファイル・2401KB)
をご参照下さい。